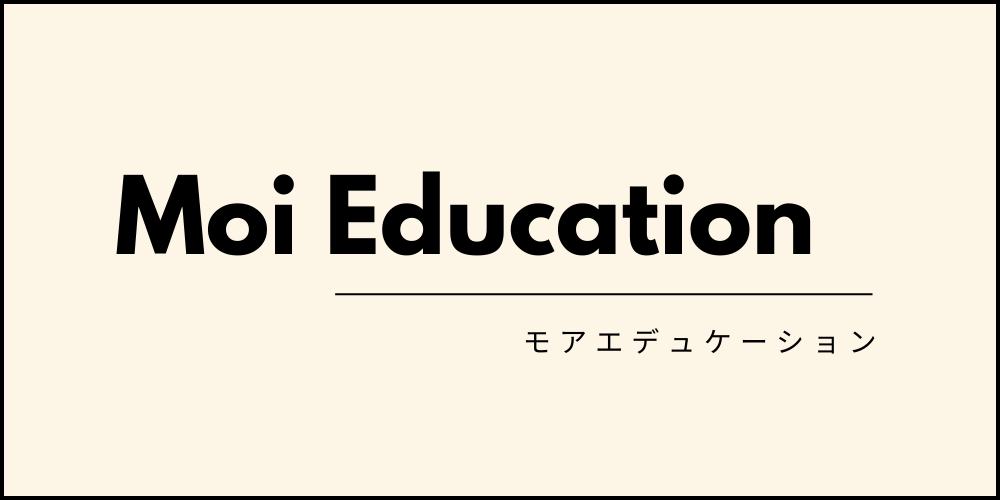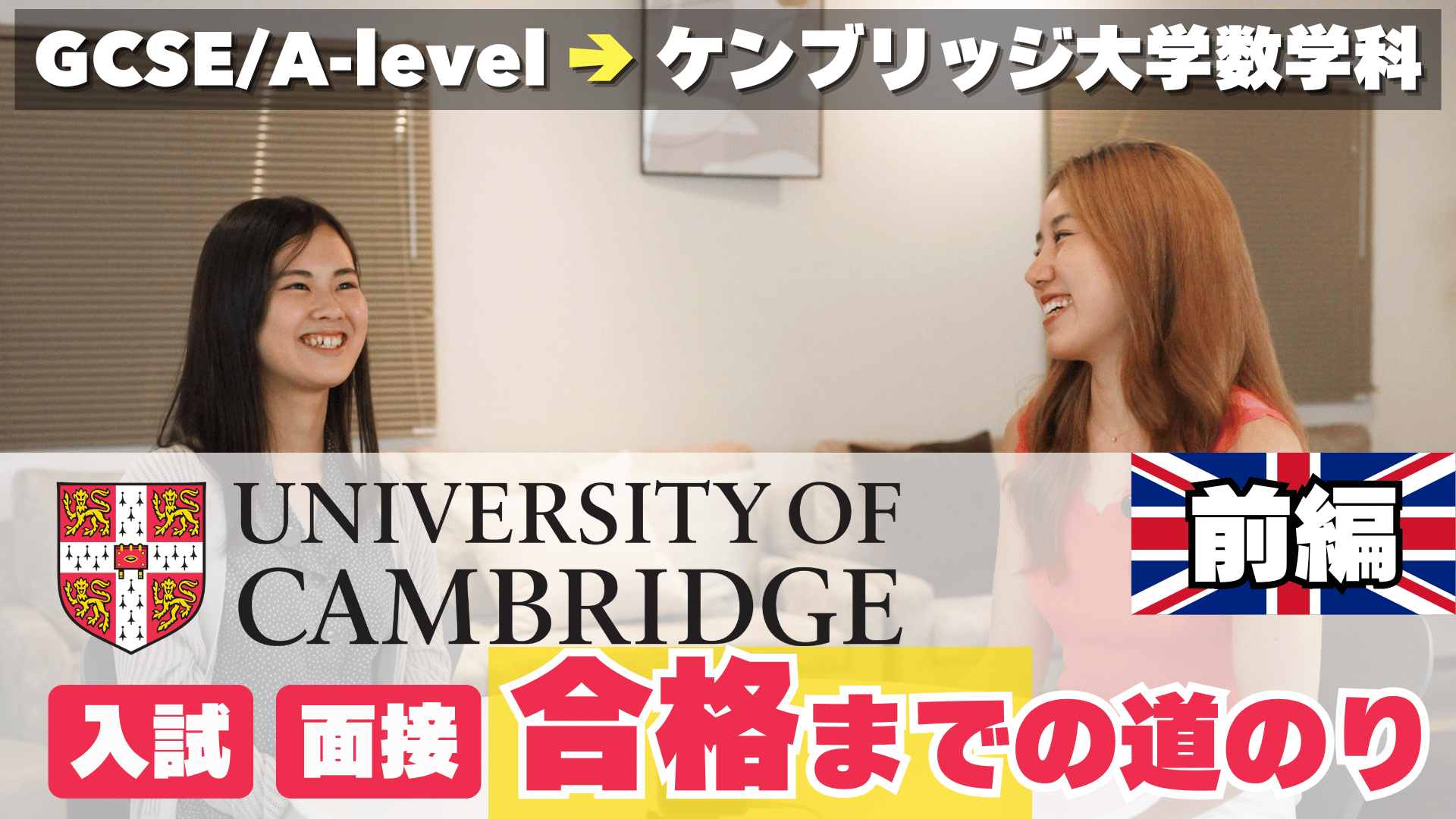【ケンブリッジ大学】現役生に合格までの道のりをインタビュー – 入試/面接対策

ケンブリッジ大学の数学科で1年生を終えたばかり*のRinと申します。よろしくお願いいたします。
*インタビュー時、2024年8月

この記事のもとになっている対談はこちらからご覧いただけます!
この記事は【前編】です。記事の最後に後編のリンクを貼っているので是非一緒にご覧ください!
イギリスでのGCSEとA-level課程
今までの海外経験
10年前に父の仕事の都合で家族でロンドンに引っ越しました。そこからずっとロンドンの公立校に通って、GCSE、A-levelと受けて大学を受験しました。1年ぐらい前に永住権を取得したので、学費もローカルの方と同じ£9,250*でやらせてもらっています。
ロンドンに引っ越したのがYear4の時で、Primary school(小学校)は地元のところに通って、Secondary(中学校)とSixth form(高校)は別のところに移りました。そこも公立校なんですけど、そこでYear7からYear13まで過ごしました。小さい時からイギリスにいる子は、特に駐在で来られる方はState School(公立校)が多い印象ですね。
*2024年までの金額
GCSEで取った科目は?
必修がEnglish Literature(英文学), Language(英語), Maths(数学), Sciences(理科)があります。Sciences(理科)は2つオプションがあって、Double Sciences*かTriple Sciences*かっていうのがあります。私の場合はどちらかというと理系だったので、Tripleの方を選んでいました。
選択科目は、うちの学校はHistory(歴史)かGeography(地理)どっちか取らないといけないっていうのがあったので、私はGeography(地理)を取りました。あと外国語も1つ取らないといけなかったので、みんなほとんどフランス語をやるんですけど、私はフランス語とスペイン語の2つをやりました。
Year11(高校1年生)の1年間だけ、放課後に週1でAdvanced Maths(応用数学)の授業があって、GCSEとは違うんですけど、一応Qualification(資格)の1つとしてあってそれをやってましたね。
*Double Sciences=サイエンス3科目を勉強するが2科目分の資格しか取れない
*Triple Sciences=サイエンス3科目分の資格が取れる
A-levelで取った科目は?

A-levelに進む時の科目選びは、大学でどういうコースに行きたいかを見据えて選びましたか?
私の場合は本当に好きだった科目を選んだっていう感じです。本当に文系は無理だなというか、あんまりエッセイ書きたくないなっていうのがありました。取り始めてから知ったんですけど、Biology(生物)ってテストの一環でエッセイも書くっていうのがあって、ちょっと後悔はしたんですけど、なるべく文字を書かないで済むようなMaths(数学), Further Maths(応用数学), Biology(生物), Chemistry(化学)を選びました。
この4つは、Medicine(医学科)に行く人たちのClassic combination(典型的な組み合わせ)って言われています。私も 最初の2週間〜1ヶ月ぐらいはMedicineを考えていたんですけど、大学で6年間は厳しいなって思ったので、Biochemistry(生化学), Chemistry(化学), Materials Sciences(材料科学)とかを考え始めました。とりあえず4つA-levelでやっていた科目を全部大学でやりたいみたいなのがあって、どれか捨てるのもったいなくない?っていうのがあったので、全部満遍なくできるような科目を探していました。
Further Maths(応用数学)のクラスの子たちは私を除いて7人ぐらいいたんですけど、みんなエンジニア志向でEngineering(工学)をやりたいっていう子が多かったです。Engineeringって手に職があるように感じられるじゃないですか。やっぱりそういう資格持っておいた方がいいのかなとか考え始めました。私はPhysics(物理)を取ってなかったので、普通のEngineering、例えばCivil Engineering(土木工学)とかはできないんですけど、唯一Chemical Engineering(化学工学)っていうのだけ、私の取っているA-levelでApply(出願)できたんです。
いろいろChemical Engineeringって何をやるのかなっていうのを調べていくうちに、結局数学を全部使ってるじゃんって思って、学校の先生方にも話して、数学って汎用性あるから、とりあえず取っておいたらいろんなことできるんじゃないかと思って最終的には数学専攻にしましたね。
私がPhysics(物理)を取らなかった理由としては、もともとA-level何をやりたいかって選ぶ時に、3つのSciences(化学、生物、物理)とMaths(数学)って考えてたんですよ。だからFurther Maths(応用数学)じゃなくてPhysics(物理)を取ろうかなと思ってたんですけど、学校の先生にあなたはすごいMaths(数学)できるから、Further Maths(応用数学)やったら絶対楽しめるよって言われて。Chemistry(化学), Biology(生物), Physics(物理)の中で 一番好きだったのがChemistry(化学)、その次Biology(生物)で最後にPhysics(物理)って感じだったので、とりあえず好きな2つとMaths(数学), Further Maths(応用数学)の4つにしました。

Maths(数学)が好きだったら Physics(物理)も好きそうだっていう勝手なイメージがあるんですけど、そこは違ったのでしょうか?笑
GCSEのPhysics(物理)でもそうですけど、計算ももちろんたくさんあるんですけどTheory(理論)の方もたくさんあって。私はどちらかというと当時は、何かにApply(応用)するような応用の方じゃなくて、Maths Challengeとかで出てくるようなロジックとかそっちの方が好きだったので、Physics(物理)じゃなくてFurther Maths(応用数学)でした。
さらに、遺伝系のトピックが好きだったんですよ。Biology(生物)はそういうのとかBiological molecules(生体分子)とかのトピックもGCSEであるんですけど、本当に基礎しかやっていなかったので、もうちょっとやりたいなと思ってBiology(生物)を選択したっていう感じですね。
高校での活動とイギリスの教育システム
高校での活動
私の学校は、部活動は基本的にはなくて、週2回、火曜日と水曜日の放課後にちょっと1時間課外活動みたいなのはありました。Sixth form(高校)になると、それが火曜日だけになるんですけど、Year12(Sixth form1年目)の間はみんな何かしらやらないといけなかったです。例えば F1のクラブみたいなのもあったり、スポーツをやる人もいたり、Medicine(医学)系のもあったり、いろいろありました。
私は最初Medicineの方に行ったんですけど、途中でつまらなくなって、他のことをできないかなって模索してる間に、 知り合いの同じ学校の数学の先生で、Year9(中学2年生)かYear8(中学1年生)の生徒たちにMaths Challengeの 対策をやっているクラスがあって。そのクラスでメンターみたいなことできないかって相談したら、やらせてもらえることになって、そこでその1年間はやっていました。
若いエナジーっていうか、Year9とかYear8とかの時はすごい楽しかったなっていうのを思い出しながら、それでも当時の私からしたらもっと幼いイメージだったので、どうやって教えるかっていうのは悩んだところではありましたね。自分はもういろいろすでに情報を知ってるからわかるけど、それをわからない人にどういうふうに噛み砕いて教えるかっていうのは難しかったなっていうのもありますね。

それはどういう風に工夫されたんですか?
とりあえず問題がいろいろあったので、それをまずどうやって解いてみる?って聞いてみて、わからないっていうのであればヒントをちょこちょこ出して、対話形式でやっていました。とりあえずやってくださいとは言うんですけど、全部をやってくださいじゃなくて、できるところまでやって、どこがわからないの?とちゃんと誘導してあげたらできるようになった子もいるので。それでいろいろ試行錯誤しながらやっていました。

Maths Challengeをそもそもやる子たちだから、ある程度レベルは高かったんですか?
1クラスだったんですけど、学年で6クラスぐらいあるのでトップ6分の1がいたクラスではありますね。でも公立校なので、みんながすごいできる中のトップじゃなくて、いろんな子がいる中の数学に興味がある子だったりするので、特別できる子は1人いたかいなかったかでしたね。
イギリスの学校の種類
私の学校はChurch of England Schoolといって、クリスチャン系だったので、半分の生徒が教会を通して紹介で入ってきて、もう半分がローカルの学校近くに住んでいる人たちが入れるっていう仕組みでした。年々そのローカルの エリアが狭まっていって、Siblingっていう制度もあって、兄弟がもうすでにその学校に通っていたら優先的に下の子も入れるというのがあって、どんどん入れるエリアが少なくなっていっていった感じです。
State School(公立校)でいうと、Grammar Schoolという類いのものもあって、そこはSecondary School(中学校)に入る前にYear6の秋頃に11+というテストを受けるんですね。それでいい成績を出した子がGrammar Schoolに入れて、日本でいう中学受験みたいな感じです。私の学校はGrammar schoolじゃなくて、Criteria(基準)に入れたら誰でも入れるところでした。

イギリスはState School(公立校)、Grammar School(公立中高で進学校)、Public School(私立校)など、いろんな種類がありますよね。
Public/Private School(私立校)は、同じようなバックグラウンドの人がたくさん集まるイメージです。Grammar School(公立中高で進学校)は親が教育熱心な子が多いイメージですけど、GrammarじゃないState(公立校)は本当にいろんな子がいるので、どういう子と関わるのかとかで、ソーシャルの面もやっぱりバリエーションが出てきますし 、勉強も取り返せるのかっていうのも周りの子に影響されたりするので、逆にいろんな可能性を秘めてるのかなって思います。
大学出願の準備とPersonal statementの書き方
UCAS出願の準備

ケンブリッジ大学受けられたので、UCAS*のApplication(出願)もEarly deadline(早期出願)で10月半ばまでに出しますよね。Personal statement(パーソナルステートメント)*を書き始めたのはいつですか?
私は多分特殊で、冒頭でお話ししたように、大学で何をやるか決めるのにすごい迷っていて、Year12(高校2年生)の1年間ずっと迷ってたんですよ。数学やろうって決めたのがYear13(高校3年生)の9月で、1ヶ月ぐらいしか準備する時間がなかったです。さらに、学校のInternal deadline(学校内の提出期限)もあって、それが9月末だったんですよ。
なので、パーソナルステートメント何書けるかなと思って先生に相談しに行ったら、正直Maths(数学)はAdmissions test(入試)とかもあるので、数学できたらエッセイとか文章をすごい丁寧にきらびやかに書ける必要はないから、とりあえず思っていることを書いてみてって。今まで何をやってきたかとか、何で興味があるのかっていうのを書いてみたらいいと思うよって言われました。
パーソナルステートメントを書き始めたのは9月の第1週目とかで、1週間でパパっと書いて、先生に添削してもらって、何回か校正しながら完成に近づけたという感じですね。
*UCAS=イギリスの出願ポータル
*Personal statement=志望動機書
数学科への出願を決めるまで
結局数学好きなんだなって思ったのが大きいです。他の人は絶対違うんですけど、夢を見たんですよ笑
私は最初Chemical Engineering(化学工学)をやろうかなと思って、オープンデイとかもChemical Engineeringでいろいろ大学を回っていたんですけど、ある日夢を見て。私はChemical Engineeringの学生をやっていて、同じ大学のキャンパスに数学をやっている子たちを見かけて、なんか羨ましいなって感じたっていうのがあって。それはもう何かのサインなのかなと思って、数学に振り返りました。
それもあったし、周りの人たちから「あなたはすごく数学できるんだからやってみたら」っていうのもあって。あともう1つ大きいのは、ちょっと数学から逃げていたんですよ。Year10か11の春休みに、Maths Challengeでそこそこ成績が良かった人たちが招待されるキャンプがあったんですね。それは通常はサマーキャンプっていう形でどこかイギリスの大学、例えばリーズ大学に集まって合宿があるんです。当時はコロナだったのでオンラインでキャンプする形になって、それに参加したんですけど、周りの子たちのレベルが高すぎて、もうこれ知ってるの?とか、大学で習うようなこともちょっと知ってたりして衝撃でした。
私はここまでは出来ないと思って、数学を大学でやるとしたら、周りがこんなに出来る子たちばかりになるから怖いっていうのも少しあって、Year12の時はちょっと逃げてたんですね。Year13に入って、「でもあれに参加した人たちって結局いても200人とかでしょう」っていうマインドセットになって。いろんな大学があるし、数学科って別に全国で200人じゃないから、自分が入ってもなんとかなるでしょうっていう思いになりました。
そういう考えに変わったので、じゃあやっぱりとりあえずやってみようって思えました。あとは、社会人になったら 周りができる人たちばかりになる環境やシチュエーションって結構あると思うので、とりあえず大学に入って慣れておこうかなっていうのもあって、それで最終的に数学で落ち着きました。
回復できたというか、自分で「どうせできない」っていうところから「やってみるか」となった変化がやっぱり大きいなと思います。
Personal statement(志望動機書)

数学科に出願するにあたり、パーソナルステートメントにはどんなことを書きましたか?
まず私にあったのが、Maths Challengeが大きかったです。Maths Challengeでキャンプに行ったことや、Maths Challenge自体は2ポンドくらい払えば誰でも受けられるんですけど、そこでいい成績を収めた人たちが招待される KangarooとかOlympiadっていうのがあって。そのOlympiadに、私はコロナの時を除いて毎年参加していたのでそのことだったり、学校でMaths Challengeで一番成績良かったという実績があったので、それをちょっと加えたりとか。
それだけで1ページ埋められないので、とりあえずA-levelのMaths(数学), Further Maths(応用数学)で一番好きな科目のことを調べて、先生に聞いたりとかして書いてみました。あともう1つやったのは、Chemistry(化学)とBiology(生物)も好きだったので、そこで何か数学と結び付けられないかって考えた時に、やっぱり統計とかは応用しやすいので、統計のことをちょろっと書きました。
でも、本やレクチャー(大学の講義)、ポッドキャストとかは一切パーソナルステートメント用には見てないし、読んでないですね。本について書いていた友達もいて、大衆向けのものだとFermat’s Last Theorem(テルマーの最終定理)の話を書いてる本があったりします。でも、ほとんどの数学書ってやっぱり高度な数学を載せているというか、証明とかが入っていて難しいなっていう先入観があって、本は読みたくないなっていうので、とりあえず実践的に過去にやっていたものを書いていくスタイルでやっていました。
志望校選び
5つ出願できる中で、スコットランドとかそっちの遠いところは行きたくなかったので、ロンドン周辺だったりロンドン内の大学で数学に強い大学を先生に教えてもらって、そのTop5を選んだっていう形です。大学ランキングも見たりしました。
ケンブリッジ大学とオックスフォード大学はどちらかしか選べなくて、Admissions test(入試)もそれぞれで違ってくるんですよ。いろいろ考慮した上で。ケンブリッジ大学の方がいいなっていうのがあったのでケンブリッジ大学にApply(出願)しました。他は全部ロンドンの大学 – インペリアルカレッジロンドン、UCL、 キングスカレッジロンドン(KCL)、プラス、ウォーリック大学に出願しました。
ケンブリッジ大学の入試と面接 – 対策方法
オックスフォード大学との入試比較

ケンブリッジ大学とオックスフォード大学で言ったら、イメージとしてオックスフォード大学は文系の方が有名で、ケンブリッジ大学は理系みたいなイメージなんですけど、実際はどうですか?
全体的にはそういうイメージって合っています。それを言ったらオックスフォード大学の人に怒られるかもしれないですけど笑
数学に関しては、Admissions test(入試)で主なものが2つあって、STEPっていうのとMATっていうのがあるんですね。STEPはMATよりも数倍難しいと言われていて、STEPを取り入れている大学がケンブリッジ大学で、MATは逆にオックスフォード大学が運営しているという背景もあって、数学においてはケンブリッジ大学の方が難しいって言われています。
なので、とりあえず難しいところ受けてみるかっていうのと、あとAdmissions test(入試)の時期も違うんですね。MATは11月に行われるんですけど、STEPの方はA-level試験と同じ時期で6月にあります。 9月に数学やるって決めたので、MATまでの時間が1ヶ月くらいしかなくて、もうちょっと準備期間が欲しいなっていうことがあって。もうちょっと入念に準備したいなって考えた時に、STEPの方が猶予があったということもあります。
カレッジごとの出願
オックスフォード大学とケンブリッジ大学はCollegiate university(カレッジ制大学)と言って、たくさんのカレッジからなっている大学です。出願する時はUniversity of Cambridge(大学)に出願するんじゃなくて、各カレッジにするんですね。
私の場合はClare College(クレアカレッジ)といって、ケンブリッジ大学の中ではMusic(音楽)に長けてると言われているところに出願しました。面接も全部Clare Collegeの教授がやってくださって、そのままオファー*をいただいて で、STEPを受けてっていう感じでした。
私の受けた前の年は、Admissions statistics(入試統計)が、Clare Collegeにおいては8割ぐらいがインタビューをもらえて、そのうち半分がオファーをもらえて、またさらに半分がSTEPを乗り越えるという感じでした。4分の1弱ぐらいならいけそうかなと思って出願したんですけど、私の受けた年の統計を見たら、やっぱりみんなそう思ったのか、入った人は結局6分の1弱ぐらいになっていて、それは驚きでした。みんな同じこと考えるんだなって笑

ケンブリッジ大学は、Admissions test(入試)がオファー出た後にあることが多いんですか?
それがSTEPだけなんです。ちなみにケンブリッジ大学の学部っていうのは、ほとんどAdmissions test(入試)があるんですけど、オックスフォード大学は例えばBiochemistry(生化学)だったらなくて、あるのとないので分かれています。
STEP以外のAdmissions testは全部11月とかそのあたりなので、インタビューの前にあることが多いです。例えば、ケンブリッジ大学独特の学部であるNatural Sciences(自然科学)だったら、NSAAというテストがあったり、Engineering(工学)だったらENGAAっていうのがあります。
*オファー=合格通知。条件付きのことがほとんど
インタビュー(面接)について
インタビューも、すごいできたって感じた子はオファーをもらえなかったり、全然できなかったって思った子がもらえたりっていうことをよく耳にするので、教授は「教えたい人に教えたい」というのがあります。よく言われるのが ‘Teachableな’ 生徒が欲しいので、1人で何も口にせず全部頭の中で解いちゃう子とかは教えにくいと言われています。だから、ちゃんと頭にあるものを口に出すっていう練習が必要なのかなって思います。
その傾向がより顕著に出るのがオックスフォード大学で、ケンブリッジ大学はIMO(International Mathematical Olympiad)、いわゆる数学オリンピックに出てた人がたくさんいるので、そこまでコミュニケーション能力に問題がない限り入れます。
そういう有名人は結構もう事前に教授が知っている場合もあったりするのかな、そういう有名人は入りやすいんだろうなとは思いますね。特にTrinity College(トリニティカレッジ)っていうのがすごい数学で有名なんですけど、みんなそういう有名人はそこに行っています。Trinity Collegeは一番お金を持っているカレッジで、アイザック・ニュートンなど有名人を輩出していて有名ですね。

インタビューはどのように行われるんですか?
私の場合は、カレッジに在籍する教授と行いました。カレッジによっては在籍している教授が1-2人の場合もあるので、その場合は他のカレッジの面接官が面接することもあるみたいです。
カレッジは1つしか出願できないので、私はClare Collegeにして、どこのカレッジがいいか決まってない子はOpen applicationと言って、ケンブリッジ大学のDepartment(学部)に出願する形になるのかなと思います。その場合は余裕があるカレッジの教授が面接する形にはなります。
オックスフォード大学とケンブリッジ大学でもう1つある特殊なシステムが ‘Pool system’と言って、出願したカレッジは定員が埋まってしまって受け入れられないけど、他の空いているところだったら受け入れられるよっていうシステムです。プールされたカレッジの教授とまたもう1回面接がある場合が多いみたいですね。
Clare Collegeを選んだ理由
さっきは統計とかって言ってたんですけど、それは後々知った情報でして、実際はオープンデーにYear12の夏に行ったんですよ。その時はChemical Engineering(化学工学)を取りたいなと思って行ったんですけど、カレッジも訪問できるということで、Kings College(キングスカレッジ)、Trinity College(トリニティカレッジ)、Clare College(クレアカレッジ)に行きました。
KingsとTrinityは、本当に敷地とか建物が壮大すぎて、ここで3年間住めるかなっていう思いがあって。それより公園っぽいっていうか、フレンドリーなカレッジとしてClare Collegeは知られているので、過ごしやすい方に住みたいなと思ってClare Collegeにしました。
あまり考えずにその3つを見に行ったんですけど、友達がここ行きたいっていうところに行ったっていう感じです。KingsとTrinityはとりあえず有名だから行こうかっていうので、Clareは、KingsとTrinityとTrinity Hall(トリニティホール)っていうカレッジもあるんですけど、その間にあって近かったっていうのも1つあるのかなと思いますね。あとは雰囲気がぱっと見好きでした。
実はインペリアルカレッジロンドンにオープンデイで行った時、正直Chemical Engineering(化学工学)だったらインペリアルの方がいいかなと思ったんですね。というのも、ケンブリッジ大学のChemical Engineeringはもっとアカデミックなので、プレゼンの仕方だったりInterpersonal skills(対人スキル)の授業はほとんどない印象で、研究研究って感じでした。
どちらかというと、私はもうちょっとそういったソフトスキルの授業も受けてみたいなっていうのがあって、Chemical Engineeringにおいてはインペリアルの方がいいかなって思いました。あとは単純に、ケンブリッジ大学のChemical EngineeringのDepartment(学部)がすごい遠くて、それ毎朝通うの面倒くさいなって感じて。だからケンブリッジ大学はとりあえず観光するだけでいっかっていう程度で行ったので、事前に情報収集っていうのはあんまりしなかったです。

学部によっても違うと思うんですけど、一般的に言うとオックスブリッジってトラディショナルな感じですよね。
そうですね。インペリアルのオープンデイに行った時にお話した在校生の方が、まさにケンブリッジ大学からオファーをもらったけど蹴ってインペリに行ったっていうことだったので、それにちょっと感化されたっていうのはあるのかなと思います。
ケンブリッジ大学数学科の面接
面接は私は2回ありました。各20分ぐらいで短い面接だったんですけど、各回で2問数学の問題を出されてそれを解いてみてっていう感じでした。カレッジの中にApplied Mathematics(応用数学)の教授がいたり、Pure Mathematics(純粋数学)の人もいたりします。
問題自体は、聞かれたのはNumber theory(整数)問題が1個と、グラフを書いてみようっていうのが2問ぐらいと、もう1つは何だったか忘れちゃったんですけど。大体そういう基礎知識ぐらいで、A-levelとかGCSEのレベルで答えようと思えば答えられるっていう問題が多いですね。

数学以外のパーソナルな質問も聞かれましたか?
聞かれる人は聞かれるんですけど、私の場合は一切聞かれずに、とりあえず自己紹介されてじゃあこの問題、みたいな感じでした。多分時間がなかったのかなと思います。結構かつかつで、20分経ったら問題の途中でも次があるからごめんねって言って。普通だったら “Do you have any questions?”って言われて質問とかできるんですけど、それもなくて “Do you have any urgent, absolutely urgent questions?”って言われて、あ、じゃあないですって言って、じゃあByeみたいな感じで終わりました笑
面接の準備は、学校の先生がそういう場を設けてくれました。数学の先生なんですけど、こういう形で行われるだろうからとりあえず問題を何個か用意してもらって、自分の頭の中にあるものを口に出すっていう練習が必要だったので、それを4回ぐらいやりましたね。
あと、グラフを描く問題はインタビューで毎年出てくるので、それは対策しようがあったのかなと思いますね。とりあえずネットで ‘Graph sketching questions cambridge interview’と調べてみて、実際に出されたのであろう質問とか他の問題を解いてみてっていうのはやりました。
オファー獲得〜A-level試験まで
オファーをもらうまで
さっき言ったAdmissions test(入試)のMATの方なんですけど、MATは11月にあって、インペリアルカレッジロンドン、ウォーリック大学、オックスフォード大学はMATで採用でした。だから、1ヶ月しか準備期間なかったけど、とりあえずMATを受けてみて、インペリアルのThreshold(基準点)より高い点を取れたので1月、2月ぐらいオファーをもらえました。ケンブリッジ大学のオファーは1月の終わりあたりだったような気がします。

私も1月にインペリアルのオファーが出て、他はもう年内に出ていた感じでした。インペリアルとマンチェスター大学、キングスカレッジロンドンあたりを待っていて、インペリアル出た後も出ていなかったのでWithdraw(辞退)しました。
私の場合は キングスが一番最初に来たのかな。それが1月始まったぐらいで、次はケンブリッジ大学が来て、インペリとウォーリック大学が来ました。UCLは3月の半ばぐらいまでずっと待ってたんですけど、同じく数学でインペリアルとかUCLを受けた友達がいて、その子はインペリアルはMATが届かずだったんですけど、UCLはもうオファーをもらっていて。私UCL来ないなって思っていたらReject(不合格)されてUCL落ちちゃったんですよ。
友達に言われたのは、Early application(早期出願)でどうせケンブリッジ大学かオックスフォード大学受けてるんだろうなってUCLが思ったのか、オファーあげない選択したんじゃないかって言わたんですけど、真相はわかりませんね。
オファーのGrade(成績)は、ケンブリッジ大学がA*A*Aと、STEP 2とSTEP 3でそれぞれ1っていうグレード以上取らないといけないっていうのでした。インペリアルがA*A*AAで、4科目やってたらインペリアルだけはなぜか4科目分のを出してくるので、それはケンブリッジ大学より高かったです。それに向けてA-level勉強して、STEPも勉強してっていう感じでしたね。
A-levelの試験対策
私の学校ではYear12の頃から1学期1テストみたいな感じで、中間テストみたいなのが学期毎にあったので、それに向けてちょっとずつ勉強をしていました。毎日一定の時間勉強するというよりかは、テストの1週間前にガーってやるみたいなタイプなんですけどそれをやっていて、Year12の分は学習内容は定着してたのかなって思います。Year13は、もう本当に習った単元のところをちょっと復習するくらいでしたね。
やっぱり過去問が一番大きくて、中間テスト用にちょこちょこ過去問は解いていたんですけど、一気にExam condition(本番と同様の環境)でやり始めたのテストの2ヶ月ぐらい前の春休み中でした。
正直、Maths(数学)とFurther Maths(応用数学)は結構オーバーラップ(重複)する単元がいっぱいあるんです。だから、Year12のFurther Maths(応用数学)でやっいた単元がYear13のMaths(数学)でもう1回授業が行われるので、その間はもう大丈夫でしょうと思ってAdmissions test(入試)の対策をしてましたね。内職じゃないですけど、先生も黙認してたのでまあいっかっていう感じで。
出願で大変だったこと
一番大変だったことはやっぱり、STEPとA-levelを同時並行で勉強することですかね。
STEPにおいては、私の学校は創立15年ぐらいなんですけど、過去にケンブリッジ大学のMaths(数学科)に受かった人がいなくて。STEPを受けてた人はいたらしいんですけど、教える環境っていうのが整っていなかったんです。1人、オックスフォード大学で数学をやっていた先生が数学の先生でいたので、どういう教材を使ったほうがいいかその先生に教えてもらいました。
STEPってネットに過去問が落ちてるんですけど、Mark scheme(採点基準)がよくわからないんですね。A-levelって結局最後の答えが合っていたら、部分点もあるけど満点もらえるじゃないですか。でも、STEPにおいては最後の答えまで辿り着くのが難しいから、ほとんど部分点で点をもらえるんですけど、何を書いたら部分点をもらえるのかっていうのが明確じゃなかったりする時もあるので、採点っていうのが難しかったかもしれません。

最後まで解けないことの方が多いんですか?
そうですね。日本の2次試験でよくある、大問が1つあってそこに小問が何個かあるみたいな形で、小問の最後の方になると結構難しかったりするので、最初の半分までは行けたけど後ができないとか結構ありましたね。A-levelのChemistry(化学)とかだと途中で間違っていてもError carried forward*があるんですけど、STEPの場合は多分あまりなくて、ちゃんと最初の方もできてないといけないんです。難しいけど、その分準備期間があったので対策のしようはあるかなと思いますね。
*Error carried forward=前の問題の答えが間違いでも、次の問題での計算ステップが正しければ部分点がもらえる仕組み
【後編】はこちらから – 「ケンブリッジ大学でのスケジュール」「数学科の勉強」「サークル活動」「就活/インターン」について話しています!
Rinさんはモアエデュケーションの講師も務めていただいているので、オンライン家庭教師にご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
イギリスの大学出願について解説している動画:
University of Cambridge 公式サイト: