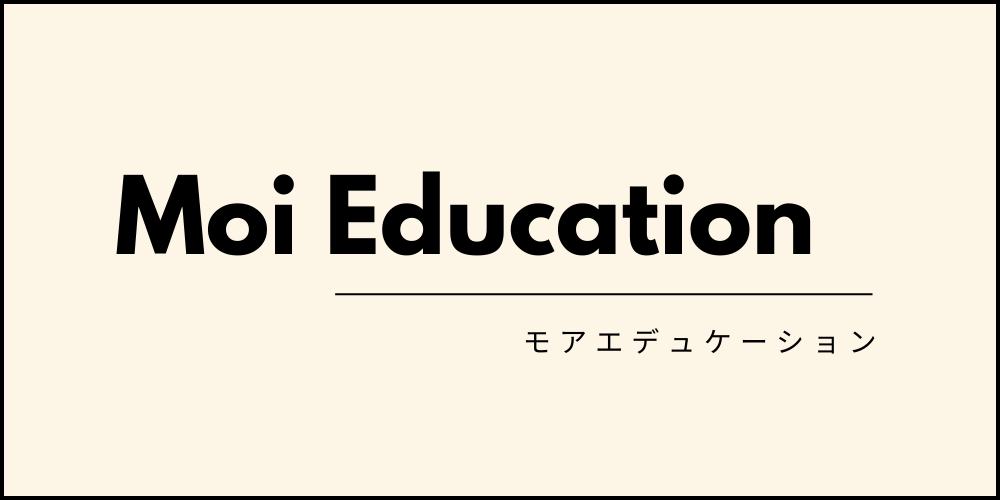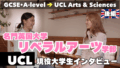英国進学校ブライトンカレッジからUCLまでの道のり【GCSE/A-level対策】

Haruhiです。
UCL(ユニバーシティカレッジロンドン)でArts and Sciencesというリベラルアーツのような専攻を学んでいます。

Haruhiさんはモアエデュケーションの家庭教師で講師としても活躍されています。GCSEレベルやKey stage threeあたりの生徒さんを指導いただいています!
イギリスの名門ボーディングスクールであり進学校で有名なBrighton Collegeでの経験から、現在のイギリスでの大学生活、講師ならではの勉強のことについても聞いていきたいと思います。
この記事のもとになっている対談はこちらからご覧いただけます!
この記事は【前編】です。記事の最後に後編のリンクを貼っているので是非一緒にご覧ください!
渡英してからの学校とGCSEについて
今までの海外経験
中1の時に父の仕事の都合で、家族みんなで一緒にブリストルに引っ越しました。それまでは東京に住んでいたのですが、その前にも5歳ぐらいまでは香港とかスイス、ドイツにも父の仕事で引っ越しをしていました。東京は幼稚園の1年と小学校の6年間だけ住んでいました。
イギリスに行って最初の学校は、家の近所の私立を探しました。寮もあったのですが、Day生(通学する生徒)として通っていました。Year7の夏学期から入ったので、イギリスでいうプレップスクール(小学校)から入って、Year11のGCSEが終わるまでその学校にいました。その後、Sixth form(Year12, 13 – 日本の高校にあたる)受験をしてブライトンのボーディングスクールBrighton CollegeにA-levelのためだけに行きました。
前の学校もSixth formがあったんですけど、別の環境でも行ってみたいなと思っていて、小学校からそこの学校で4-5年くらいいたので別の環境でも行きたいなと思って、受験することに決めました。
最終的にUCLに入ったんですが、最初から大学までずっとイギリスにいるかは決まってなかったです。父の転勤の長さが決まってなかったので、もしかしたら大学とか高校まで行くかもしれないし、日本に帰るかもしれない。最初の頃はやっぱり、日本の元々いた小学校が中高も一貫だったので、戻れる場所があったので日本に戻りたいなと思ってたことも多かったです。でも高校ぐらいから、やっぱり高校までイギリスのシステムで勉強してきたので、大学まで行くのがいいかなと思ってきました。そこまで来ると帰国受験できるほどでもなかったので、そのままイギリスで行くのがいいかなって思い始めました。
GCSEで取った科目は?
必須科目ではEnglish Literature(英文学)、English Language(英語)、Maths(数学)、Sciences(理科)は3科目をやっていたのでPhysics(物理)、Biology(生物)、Chemistry(化学)をやっていました。選択科目は4つあるんですけど、そのうち1つは言語じゃないといけないのでSpanish(スペイン語)を選択して、あとはGeography(地理)、Economics(経済)、Art(美術)を取っていました。追加でFurther Maths(応用数学)とJapanese(日本語)のGCSEも取っていたので結構多めでした。
Sixth form受験について
コロナになった時に家にいる時間が多くて色々考える時間もあって、親からも別の学校考えたりとかする?って言われて別の学校を見に行きました。通っていたのが田舎の学校だったので、もうちょっとProgressiveな学校でもいいかなって思って学校を探し始めました。
Year10の終わりぐらいの夏学期あたりに考え始めて、学校のオープンデイもちょうど6月にあったり、夏休み中にも連絡が来たりみたいな感じでした。行きたいところを何校か選んでApply(出願)しました。
大体の学校では筆記の試験があって、その後に面接が必ずついてくる学校もあれば、試験が通ったら面接に進めるタイプのところもありました。そのうちの1つのところでは英語の試験がありました。日本人なので、海外生は英語の試験を受けなきゃいけないので、ケンブリッジの試験を受けて英語レベルを証明する必要がありました。

私もSixth Form受験をしたのですが、その時はMath(数学)、English(英語)ともう1つ、自分の好きな科目での受験でした。Physics(物理)が得意だったのでMath(数学)、English(英語)、Physics(物理)の3科目プラス面接で受験したのですが、Haruhiさんの時は何科目でしたか?
実際に入ったBrighton Collegeの試験は同じような感じで、Math(数学)、English(英語)とSciences(理科)は3つのうちの2つ選んでやりました。面接は、A-levelでやりたい科目の先生との面接式の試験みたいな形式でした。オンラインだったんですけど、口頭で問題が出されて画像とかを見せられたりして、それを口頭で答えなければいけなかったので難しかったですね。
学校選びの基準
今まで行っていた学校とは違うタイプのところがいいと思っていました。例えばロンドンの学校だと、もっといる生徒もDiverse(多様)な感じになるので、そういうのもいいと思いました。人からいいと聞く学校も調べてみて、オープンデイに行って雰囲気が合うか確かめたりもしました。
元々いた学校はイギリスのトラディショナルな学校の雰囲気だったので、歴史あるところも良くてそういうところも選んだんですけど、もうちょっと新しめの学校とか勉強に力を入れてるところとかもいいなと思って選びました。
Brighton Collegeでの生活とA-level
Brighton Collegeはどんな学校?

ブライトンカレッジは進学校で有名なんですが、3分の1が寮生で、そのうちの半分ぐらいは留学生です。トラディショナルな伝統的なボーディングスクールとはまたちょっと違う雰囲気で、校舎も新しい感じですし、敷地的には比較的狭めです。ハウスシステム(寮単位で活動する)はあって、だいぶイギリスっぽい感じではあるんですけど、ブライトンっていう街自体も海の近くにあったり、いろんな人がいる街なので、活発的で若い感じです。
ロンドンの人もいっぱいいて、ブリストルの学校にいるイギリス人の寮生だとウェールズから来る人が多いんですけど、ブライトンだとロンドンから来る子たちが多くて、ほとんどの寮生はロンドンの子でした。ロンドンからだと電車で1時間ぐらいで近いのもあるかもしれません。
ブライトンの街

ブライトンのタウン(街)の中は何でもあって、ロンドンの人が多いってことで新しかったり、流行にも敏感だと思います。ブライトン駅からビーチのほうに下る途中に大きいショッピングセンターがあって、その周りが栄えています。駅の左手にIndependent shops(個人店)とか小さめのお店がいっぱい並んでいる通りが何個かあって、その辺りが一番人が集まってるかなっていう印象です。

私は旅行で行ったことがあって、道沿いでシーフードを食べた記憶があります!Brighton Pier(桟橋)の近くは遊園地もあって、その辺りも賑わっていて楽しい街っていうイメージがあります。
日本人でもサッカーチームがあるからブライトンを知っている人が多かったり、最近は三笘選手など日本人プレーヤーもいるので知名度が上がってきたのではないでしょうか。
ブライトンのアルビオンの試合を観に行ったことがあります。三笘選手は出ていなかったんですが、日本人もいっぱいいたかなという印象でした。

サッカー好きなんですか?
サッカーは海外の国際試合とかしかあまり観ないんですけど、最近はユーロカップとか観ていて、ワールドカップとかたまにプレミアリーグ観るくらいです。
どちらかというと弟がラグビーをやってたので、家族ではラグビーの方が観る機会多いですね。 弟は3歳くらいの時からラグビーをやっていて、今もイギリスで続けてやってます。
A-levelで取った科目は?
A-levelはMaths(数学)、Biology(生物)、Geography(地理)を取りました。1年目はArt(美術)も取ってたんですけど、2年目に上がるタイミングで落としました。好きな科目で比較的得意な科目で選びました。
A-level何取るかが大学選びにも重要になってくるので考えたんですけど、まずガッツリ理系は多分行かなそうでした。生物が比較的弱めの理系って思われていて、化学か物理を取っていないとガッツリ理系の学部に入るのは難しかったりするんですが、その方向には行かないからどっちも取る必要はないかなと思いました。数学はどの学部に入るのにも使えそうだったからという理由です。逆にガッツリ文系とかEnglish(英語)とかもそこまで興味がなかったあので、好きな科目を4つ選びました。
Art foundationを一時期考えていたので、そのためにArt(美術)を取ってたんですけど、1年目の終わりぐらいにやっぱりその道はないと思ったというのと、時間がいくらでもかかってしまって他の科目の成績が大変なことになってきたので、落とすことにしました。

私は医学部志望だったので、完全に理系の科目に絞ってMaths(数学), Chemistry(化学), Biology(生物)を取りました。
文系の科目はエッセイや、Art(美術)に関してはプロジェクトが多かったり、ワークロードが多くて大変なイメージがあります。良いグレード取るのも、プロジェクトなどは学校の先生が採点するのでちょっと難しいイメージです。
そうですね。Art(美術)もエッセイがあって、プロジェクトの善し悪しは学校の先生基準でグレードを出していました。それを本番の試験ではExaminer(試験官)の人が来て、学校の先生が出したPrediction(予測グレード)で合っているのかチェックする感じなので判断があやふやだったり、先生との相性がダメだとグレードが悪くなっちゃう人もいたりします。
Geography(地理)も全部エッセイなので1問が20 marker(20点問題)や9 marker(9点問題)となっていました。その点数の判定を先生たちが厳しくしてたので、普段はずっと点数が取れてないと思うけど、それが実際の試験でどうなってるのかもよくわからない感じのままA-levelまで行っていました。
Geography(地理)について

私はGCSEの時にGeography(地理)を取っていました。One-year GCSEコースだったので1年しかやっていなくて、最初は英語も弱かったのでエッセイ多い科目は大変でした。理系の科目はMark scheme(採点基準)がしっかりあるのに対して、私の場合は文系の科目がGeography(地理)とEnglish(英語)だけだったのですが、やっぱり採点基準がよく分からなくて伸ばすの大変でした。
Geography(地理)に関しては、GCSEレベルでもケーススタディを覚えるというのがメインになりますよね。例えば中国のOne-child policy(一人っ子政策)とか、どこかの国の地震のこととか。日本も出てきたり、台風のケーススタディとかもありましたね。
地質や岩のタイプ、Coast(海岸地形)とかもありました。日本で地理っていうと、各地の名所を覚えて特産品を暗記して、それをテストで穴埋めで書くのが多いと思うんですけど、イギリスの地理は「地学」みたいな感じで、暗記もあるけど、調査してそれをエッセイにまとめ上げるのが特徴だと思います。
地学も多いですし、A-levelだと経済っぽい地理とかも出てきたりします。経済とか政治関連のこととか、日本でいう公民に近いものもやるので、幅が広くなって覚えることも増えるって感じでした。
サークル活動とピアノ
課外活動は、スポーツはそこまでやっていなかったんですけど、学校のアクティビティとしてダンスやフィットネスをやっていました。音楽はピアノを弾いてたので、ピアノのレッスンを学校で取っていました。
ピアノは高校に入る前にABRSM(英国王立音楽検定)のGrade8まで取っていました。高校の時もディプロマのシラバスに乗っかってやってたんですけど、結構忙しかったので実際に取るのはやめて、それに載っている曲を弾いていました。
他のアクティビティでいうと、友達とディスカッショングループをやっていました。上の学年になると自分でSociety(サークル)を作ることができるので、友達が作った、色んなことをプレゼンしたり自分の好きなトピックに関してディベートしたりするSocietyに入って、そこに毎週参加していました。勉強関連のSocietyにも入っていましたね。
大学出願とPersonal statement
専攻を決めたのはいつ?
A-level 1年目の3学期ぐらいから、自分が興味ある範囲でReading*を始めました。心理学に興味があったので、それの周りのReadingをしたり、大学の学部を見てコースの内容をチェックしたりして、3学期目ぐらいにはどういう学部にしたいかは決めるようにしてました。
出願した学部は、UCLのArts and Sciencesとその他4校は心理学部で出しました。イギリスにArts and Sciencesの学部があまりなくて、UCLほど上手く構成されているところもなかったので、特別行きたくない大学の学部に入るようだったら心理学にも興味があるし、心理学部で受けたいかなと思っていました。

A-level科目にPsychology(心理学)もあったんですけど、心理学部に入りたいかどうかわからなかったし、上の方の大学の心理学部だとA-levelで心理学をやっている人よりも、理系の科目を2つ以上取ってる人の方が優遇されるって聞いたりしました。学部にもよるんですけど、ガッツリ理系で統計とかもやらないといけなかったり、Lab work(実験)も結構あって、やっぱり理系やってる方がいいと言われていました。特に3科目しか選べない中で他にもやりたい科目があったので、心理学は選ばないでおきました。

大学で心理学を専攻する場合でも、A-levelでPsychology(心理学)を取らなくてもいいんですね。
大学によっては、サイエンス3科目(化学・生物・物理)、Maths(数学)ともしかしたらPsychology(心理学)のうちの1つか2つA-levelで取っているのがPreferred(好ましい)と書いてあるので、Psychology(心理学)を取っていなくても入れます。Masters(修士)付きのコースはMaths(数学)が入っている方がいいと言われたりもします。ロジカルシンキングがちゃんと使えるかだったり、あと生物も心理学とオーバーラップしているところがあります。脳科学系とかNeurons(神経細胞)とか、その辺りが心理学のBiopsychology(生物心理学)の部分では重なる部分も多いです。
*Reading=本・文献・論文などを読むこと
EPQとエッセイコンペティション
UCAS*のApplication*に向けての準備は、新学期が始まる前の夏の間にしていました。その前からReadingなどは始めていましたが、夏休みの間も引き続きしていました。
アートと心理をトピックにしたEPQ*をやっていたんですけど、それは1月くらいからもう始めていましたね。それのためにもReadingしたりリサーチしたりしていたので、論文や本を読んでいました。本は、大学の学部のページに読んでおいた方がいいReading listがあるのでそれを参考にして、その中で興味がありそうなのを読んでいました。
エッセイコンペティションもやっていて、Personal statement*に書けることを増やしていきました。コンペティションをやりながらReadingもできるので、とにかく色々読んで、自分が興味あるのか見定める期間が3学期目と夏休みの間だったかなと思います。

EPQの内容もPersonal statementに書きましたか?
私の場合はEPQの内容がアート寄りだったので、それを直接書くというよりはEPQのために読んだ本とか、あとは自分が書いたエッセイコンペティションについての話を書きました。エッセイコンペティションは学校開催のものと、外部で学校の先生がこんなのありますよって送ってくれるものもあって、私は外部のを1つやりました。心理学のエッセイを書いたんですけど、用意されたテーマから一つ選んで、それに関して質問を答えるタイプのエッセイでした。
EPQのテーマは、日本の戦争時代のアートと作者(アーティスト)の心理がどう日本の戦時中と戦後のアートに影響を及ぼしているか、という事を書きました。心理学にも絡めて書いたんですけど、どちらかというとPhilosophical(哲学的)の感じのものとか、精神だったりArt history(美術史)のようなものでした。例えば、ドイツと比べて日本はどうだったかみたいなのを書いたので、そこまで心理学っぽいものではなかったと思います。
*UCAS=イギリスの大学出願ポータル
*Application=出願
*EPQ=Extended Project Qualification、授業とは別で行う任意のプロジェクトで、A-levelの0.5科目分の資格が取れる。
*Personal statement=志望動機書
A-level試験対策と出願での苦労
A-levelの試験対策

出願が終わって大学からOffer*が出たら、今度はそのOfferを満たせるようにA-levelの対策を行なっていきます。試験勉強はどのように進めていきましたか?
学校から課題や宿題がいっぱい出されたのでそれをやったり、最後の2学期ぐらいは毎週のようにクリニック(補習)があって、そこで例えばGeography(地理)は毎週Timed essay(時間を測って書くエッセイ)を書くとか、いっぱい試験の練習をさせられました。数学と生物のクリニックもあって、過去問をやって試験慣れするみたいなタイプの勉強を最後の方はしていました。
定期テストの成績が悪い人は強制クリニックがありました。A-levelは3科目しかやっていないのでフリーな時間が多いんですけど、そういう時間がフリーじゃなくなってクリニックにさせられて、数学を週8時間やらなくてはいけない、というふうになっていました。A-level 2年目は、最初から行きたければFree period*の時に全科目でクリニックは1日中やっているので、先生のところに行ってやることもできます。絶対行かないといけない人もいれば、行きたければ行ける人もいてっていう感じでした。
Brighton Collegeは学校全体の成績の底上げを、特にA-levelの最後の年は頑張ってやっていました。理系が強かったので、先生の数そっちの方が多くて、数学なんかはいっぱい先生がいました。地理とかだとそこまでいなかったですが、その中でも例えば自分が教わってない先生、本当はGCSEしか教えてない先生がクリニックはやっていたりしました。その先生たちがA-levelを教えられないわけではないので、学校全体で回している感じでした。
*Offer=合格通知。条件付き合格がほとんど
*Free period=授業のない時限
出願プロセスで大変だったこと
1年目の最後のMock*テストの成績によってPredicted grade*が決まるので、それが結構重要だったんですけど、それがあんまりうまくいかなくて。もうちょっと上げられるために夏休み明けにResit(再受験)をしたり、Mock以外でもクラス内のテストでまたいい成績を取らなくちゃいけなかったりで、Application(出願)よりA-levelの勉強面が一番苦労しました。
UCASのApplicationを進めている間で、Personal statementのためのリサーチがA-levelの方にもプラスになることもあるんですけど、Psychology(心理学)はA-levelでやっていない科目だったので、出願とA-levelが別物になっていました。そこがバラバラだったのが、時間が色々なところでかかってしまって大変だったのと、EPQもやっていたので、EPQとUCASのタイミングが被ったり学校生活の大きいイベントが被ったりして、色んなものの両立が難しいと感じました。

日本の大学受験や高校受験、中学受験もそうですが、一番最後の試験で点を取れればいいというのとは対照的に、イギリスは内申点じゃないけど、積み重ねでグレードが決まりますよね。学校の成績でPredicted gradeが出されて、それでApplicationを出すので、長期的に継続して頑張らないといけないですよね。
更にコースワークもあって、それは先にグレードが出るので先にやっておかないといけなかったです。Applicationで見られるPredicted gradeのためにはA-level 1年目からちゃんといい成績を取ってないといけなくて、最後の試験とは別物みたいな感じもあります。
*Mock=模擬試験
*Predicted grade=大学出願時に提出するA-level予測グレード
GCSE•A-level試験勉強のコツ

Haruhiさんは今、2人の生徒さんを指導いただいているのですが、IGCSE/GCSEやA-levelで良い成績を取るためのコツや勉強法はありますか?
試験になると、いくら内容が理解できていても試験で点が取りづらい科目があったりします。特にサイエンスの中では生物が難しいかなと思うんですけど、Specificな(特定の)キーワードを覚える記憶力も必要で、それをちゃんと文章化できるかというのが問われます。Flash card(暗記カード)を使っていろんなキーワードを定期的にノートして使ったり、それの練習をしたりするのがいいかなと思います。
理解の方を深めるのには、私はSpider diagramでマインドマップみたいなものを書いていました。例えば生物だと、いろいろ図とか絵に描いてみて人体の場所の名前を覚えて、それによってコネクションを考えました。地理はPhysical geography(自然地理学)とHuman geography(人文地理学)があって、別々のトピックなんですけど交わってもいるので、そこのコネクションについて考えられるとエッセイに書くときに深みが出ます。
また、過去問をいっぱい解いて、どうして間違ってるのかを分析することも大事です。Mark scheme*ではどういう風に書いてあるのかを見たり、Mark schemeのパターンを見てみるのが効果的だったと思います。
*Mark scheme=採点基準
【後編】はこちらから – 「UCLでの勉強」「Japan Societyのサークル活動」「卒業後の進路とキャリア」について話しています!
Haruhiさんはモアエデュケーションの講師も務めていただいているので、オンライン家庭教師にご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
イギリスの大学出願について解説している動画:
UCL 公式サイト: